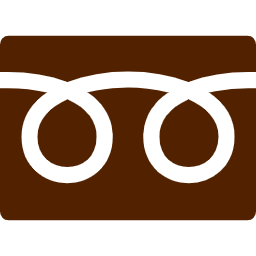おしゃぶりと歯並びの関係|いつまでOK?やめどきは?

おしゃぶりは、赤ちゃんにさまざまなメリットをもたらすものですが、同時にデメリットもあるという話をよく耳にします。例えば、おしゃぶりが歯並びに悪い影響をもたらすという投稿は、SNSなどで目にする機会がありますが、実際のところはどうなのか気になっている親御さんも多いことでしょう。
そこで今回は、おしゃぶりと歯並びの関係や赤ちゃんにおしゃぶりを使うメリット・デメリット、おしゃぶりをやめるタイミングなどを東船橋駅1分のスマイルデンタルクリニックが詳しく解説をします。
おしゃぶりと歯並びの関係
おしゃぶりは、適切な方法で使うことに何ら問題はないのですが、使用期間が長期にわたると歯並びに悪い影響を与えることがあります。具体的には、おしゃぶりの長期使用によって、歯並びに次のような変化が起こり得ます。

出っ歯・開咬になる
おしゃぶりを吸う時の力は、皆さんが想像している以上に強いです。しかもおしゃぶりを吸うという行為は、長い時間継続するため、前歯にも相応の圧力がかかります。その結果、前歯が前方に傾いたり、上下の前歯部間に隙間が生じる開咬(かいこう)の症状が現れたりするのです。とくに幼児期は顎の骨がやわらかいことから、歯も動きやすくなっている点に注意が必要です。
歯列の幅が狭くなる
おしゃぶりを長期間にわたって使用していると、歯列の幅が狭くなることがあります。専門的には歯列弓の狭窄と呼ばれる症状で、上下の噛み合わせが悪くなることに加え、永久歯が生えてくるスペースが不足して、乱ぐい歯(叢生)や交叉咬合など、さらなる歯並び・噛み合わせのトラブルを引き起こしかねないため注意しなければなりません。
赤ちゃんにおしゃぶりを使うメリット・デメリット

続いて、赤ちゃんにおしゃぶりを使うメリットを解説します。
メリット1:リラックスできる
赤ちゃんにおしゃぶりを使うメリットとしては、第一にリラックス効果が挙げられます。赤ちゃんには、お母さんのおっぱいを吸うための「吸啜反射(きゅうてつはんしゃ)」が備わっており、何かを吸っている状態は安心感へとつながります。乳幼児期に見られる指しゃぶりも安心感を得るために行うものなのです。それをおしゃぶりで代替できることは、赤ちゃんにとってメリットといえます。
メリット2:指しゃぶりを防止できる
指しゃぶりもおしゃぶりと同じような効果が得られる習癖ですが、衛生的な観点からはあまり良いものとはいえません。赤ちゃんはいろいろなものを分別なく触る傾向があるため、汚れた手で指しゃぶりをすることも厭いません。それならばきちんとケアされたおしゃぶりでリラックス効果を得た方が赤ちゃんの健康においても良いといえます。
ちなみに、おしゃぶりは物を使った習慣なので、やめる、あるいはやめさせることはそれほど難しくありませんが、指しゃぶりは自分の指を使った習慣であることから簡単にやめることはできません。こうした点からもおしゃぶりで指しゃぶりを防止するメリットは大きいと言えます。
メリット3:鼻呼吸を促せる
おしゃぶりを使っていると、お口周りの筋肉が発達します。おしゃぶりを咥えていること自体が口腔周囲筋のトレーニングとなり、口を閉じる力が養われるのです。その結果、幼児によく見られるお口ぽかん(口呼吸)が改善され、鼻呼吸が促されます。鼻呼吸は細菌やウイルスによる感染症を予防しやすくなるだけでなく、お口の乾燥を防ぐことで歯周病や虫歯の予防効果も高まります。さらには、歯に対して適切な圧力がかかることから、歯並びが悪くなるのも防いでくれます。実際、欧米諸国では、子どもの口呼吸を改善する目的でおしゃぶりを使うことがあります。
このように、おしゃぶりにはたくさんのメリットがありますが、いくつかデメリットも伴う点に注意しましょう。
デメリット1:歯並びに悪い影響をもたらす
上段で述べた通り、おしゃぶりの長期使用は歯並びに悪影響をもたらします。そこで気になるのが「長期使用」とはどのくらいなのかという点です。一般的には、おしゃぶりを生後18ヵ月くらいまで使用しても、歯並びに深刻な悪影響をもたらすことは少ないと考えられています。一方、生後19ヵ月以降も継続して使い続けると、開咬や出っ歯になりやすいことがわかっています。もちろん、これはあくまで目安であり、子どもの発育には個人差が見られることから、すべてのお子さんに共通しているわけでないので、おしゃぶりの使用でどうなるかはケースバイケースと言えます。
デメリット2:子どもの感情を読み取りにくくなる
乳幼児は、いろいろな理由で泣いたり、駄々をこねたりします。一見すると、何の意味もないような行為や感情の発露に見えますが、実際は一つひとつに意味があると言っても間違いではありません。そこでおしゃぶりを使うと、子どもの情緒は安定するものの、なぜ泣いたのか、なぜ駄々をこねたのかを汲み取らないままその場をやり過ごしてしまいます。その積み重ねが子どもとの深刻なコミュニケーション不足になる可能性も否定はできません。
デメリット3:やめさせるタイミングや方法が難しい
おしゃぶりは、子どもにとって心強い精神安定剤となることから、それをやめさせるタイミングや方法で悩まされるケースが多々あります。この点は後段で詳しく解説します。
おしゃぶりのやめどきと卒業方法
最後に、子どものおしゃぶりをやめさせるタイミングと卒業方法について解説します。

やめどきは2歳頃
子どものおしゃぶりは、2歳頃までにやめるのが理想です。前述した通り、おしゃぶりの使用が生後18ヵ月以降も継続すると、歯並びに影響が現れやすくなるからです。ちなみに、1歳半から2歳にかけては、乳歯の奥歯も生えてくるため、子どものお口が「吸う」
ことから「噛む」ことへと構造変化していきます。
おしゃぶりの卒業方法
おしゃぶりは、使用頻度を徐々に減らしていきながら、段階的に卒業するのが望ましいです。おしゃぶりの必要性を低下させるためには、親御さんがたくさん話しかけたり、絵本を読んで気をそらしたりすることが大切です。おしゃぶりがなければ眠れないような場合は、日中の運動量を増やしてみてください。公園での外遊びで体力を使い切ると、おしゃぶりなしでも眠れることが多いです。それでもなお、おしゃぶりへの依存度が低下しない場合は、おしゃぶりの先端をカットしたり、強制的におしゃぶりを子どもが触れない場所に隠したりするのもひとつの方法です。
まとめ
今回は、おしゃぶりと歯並びの関係について、東船橋駅1分のスマイルデンタルクリニックが解説しました。おしゃぶりは、乳幼児期にとても重要な役割を果たすアイテムですが、長期間使用すると歯並びに悪い影響をもたらすことがわかっています。そんなおしゃぶりの使用で子どもの歯並びがどうなるか不安、おしゃぶりによる歯並びへの悪影響を取り除きたいと考えている方は、当院までお気軽にご相談ください。
院長 椎名 康雅
最新記事 by 院長 椎名 康雅 (全て見る)
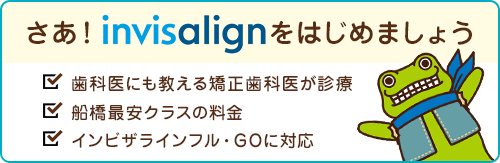
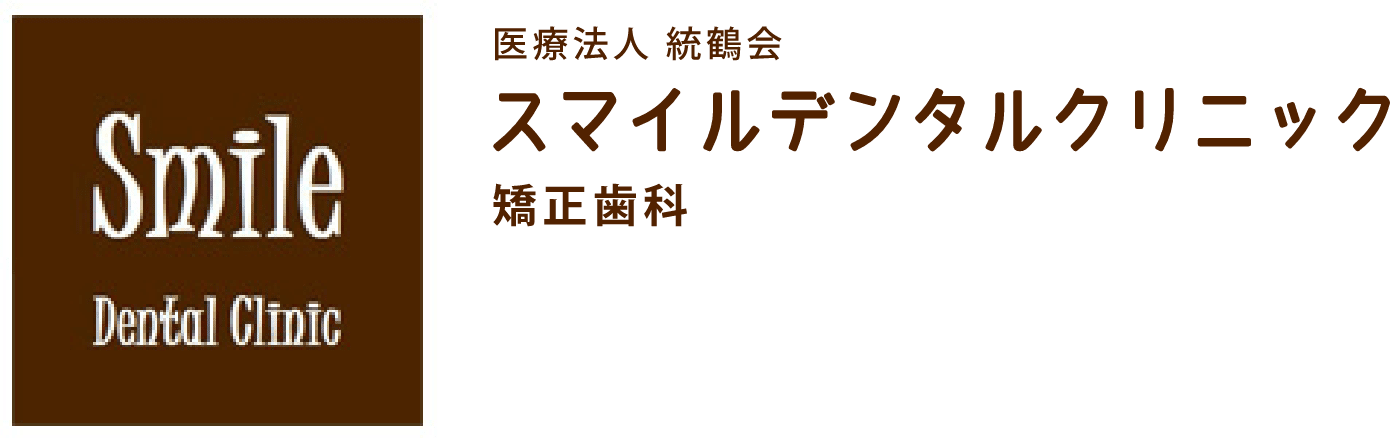
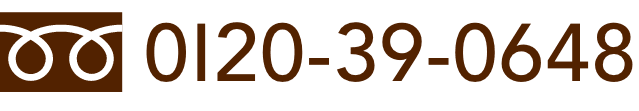
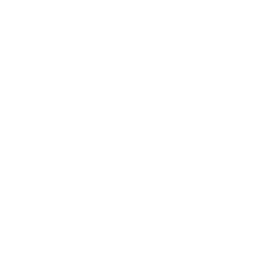 0120-39-0648
0120-39-0648