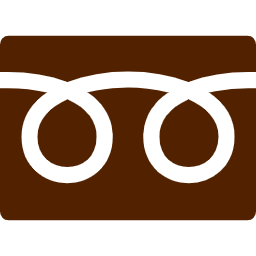夜間授乳はいつまで?虫歯リスクとやめどきの目安を小児歯科医が解説

皆さん、こんにちは。小児歯科医として日々診療を行っていると、「夜間授乳はいつまで続けていいのでしょうか?」というご質問を多くいただきます。母乳やミルクは赤ちゃんの成長に欠かせない栄養ですが、長期間の夜間授乳は虫歯のリスクを高める要因になることが知られています。
特に睡眠中は唾液の分泌が減少し、歯に糖分が停滞しやすいため注意が必要です。本コラムでは、夜間授乳と虫歯の関係、やめどきの目安、また続ける場合の虫歯予防策について、小児歯科の立場からわかりやすく解説します。
夜間授乳はいつまで続けていいの?
1歳を目安に減らしていく
夜間授乳は、新生児期から乳児期にかけては栄養補給や情緒的な安定のために自然かつ重要な行為です。しかし、生後6か月を過ぎると離乳食が始まり、徐々に母乳やミルク以外からも必要な栄養素を摂取できるようになります。1歳前後になると、鉄分やタンパク質など成長に欠かせない栄養素は食事からの摂取が主体となり、夜間授乳の必要性は次第に低下していきます。小児科や小児歯科の見解でも、「1歳を目安に夜間授乳を減らしていくことが望ましい」とされており、これは栄養学的観点だけでなく、口腔衛生上の理由からも推奨されています。
2歳を超えるとリスク増加
2歳以降も夜間授乳を継続すると、虫歯や歯茎の炎症リスクが顕著に高まります。特に乳歯はエナメル質が永久歯に比べて薄く酸に弱いため、夜間に口腔内へ糖分が長時間残留すると、短期間で虫歯が進行する恐れがあります。さらに睡眠中は唾液の分泌が低下するため、母乳やミルクに含まれる乳糖が歯の表面に付着したままになりやすく、虫歯菌による脱灰を助長します。とくに上の前歯は唾液による自浄作用が届きにくく、哺乳びん虫歯の好発部位として知られています。
そのため「夜間授乳はいつまで?」という問いに対しては、「1歳を過ぎたら回数を徐々に減らし、2歳までには卒乳を検討するのが理想的」と言えるでしょう。これは虫歯リスクを抑えるだけでなく、顎や歯列の健全な発育を促すうえでも重要なステップとなります。

夜間授乳と虫歯の深い関係
唾液分泌の減少と虫歯菌の活動
唾液は口腔内の自浄作用や再石灰化を担う重要な生理機能を持っています。唾液に含まれるカルシウムやリン酸は、酸によって溶かされた歯の表面を修復する働きがあります。しかし睡眠中は副交感神経優位となり、唾液分泌量が大きく減少します。そのため、母乳やミルクに含まれる乳糖(ラクトース)が歯の表面に長時間停滞し、ストレプトコッカス・ミュータンスなどの虫歯菌が乳糖を代謝して酸を産生し、歯のエナメル質を脱灰するリスクが高まります。
「哺乳びん虫歯」のリスク
夜間授乳が長期間続くと、上顎前歯を中心に「哺乳びん虫歯(う蝕)」と呼ばれる特徴的な虫歯が見られることがあります。これは、哺乳びんや授乳姿勢により糖分を含む液体が前歯に停滞するために生じやすい病態です。放置すると、前歯の歯冠が大きく崩壊し、審美性の低下だけでなく、発音への影響や食べ物を噛み切る機能の低下を招く可能性があります。また乳歯は永久歯の萌出誘導路を担うため、重度の虫歯は永久歯の生え方や噛み合わせにも悪影響を及ぼしかねません。
噛み合わせや顎の発育への影響
夜間授乳の継続は、虫歯リスクだけでなく、歯列や顎の発育にも間接的な影響を与える場合があります。たとえば、授乳時に常に同じ姿勢をとる習慣が続くと、顎の左右バランスの発達に偏りが生じ、噛み合わせの不調和を招く可能性があります。さらに、虫歯による早期の歯の喪失は、隣接歯の移動や咬合不全を引き起こし、顎骨の成長に悪影響を及ぼすこともあります。
夜間授乳を続ける場合の虫歯予防

授乳後の口腔ケア
夜間授乳を完全にやめるのが難しいお子様も多くいらっしゃいます。その場合、授乳後のケアが重要です。乳歯はエナメル質が薄く酸への抵抗力が弱いため、虫歯の進行が早い傾向があります。授乳後はガーゼや綿棒を水で湿らせて歯や歯茎をやさしく拭い、口腔内に残った乳糖を取り除くことが推奨されます。数本以上の歯が萌出してきたら、寝かしつけの前に歯ブラシを用いた清掃を習慣化することが理想です。歯磨き粉を嫌がる場合でも、歯ブラシで機械的にプラークを除去するだけで十分な予防効果が得られます。
フッ素の活用
フッ素は再石灰化を促進し、エナメル質を酸に溶けにくくする作用があります。夜間授乳を継続する場合には、市販のフッ素入り歯磨剤を米粒大の量から使用することが効果的です。また、歯科医院での定期的なフッ素塗布やフッ化物洗口も予防策として有効です。特に、歯科医院で使用する高濃度フッ素(9000ppm程度)は市販品より強い効果が期待でき、定期的な歯科受診と併用することで虫歯の発症リスクを低減できます。
夜間授乳をやめるときのステップ

ステップ1:授乳回数を徐々に減らす
夜間授乳を急に中止すると、子供の強い不安や泣きが続き、親子ともに大きなストレスとなることがあります。そのため、まずは授乳回数を段階的に減らしていくことが大切です。例えば、夜中に3回授乳していた場合は、数日〜1週間ごとに1回減らし、体が新しいリズムに慣れていくようにします。こうした「漸減法」によって、子供の自律的な睡眠リズムの確立も促されます。
ステップ2:安心できる環境を整える
夜間授乳は栄養補給だけでなく、子供にとって「安心感の源」でもあります。その代替として、添い寝や抱っこ、背中をさすってあげるなど、非栄養的な安心手段を取り入れることが有効です。特に、一定の環境(暗さ・室温・寝具の快適さ)を整えることは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を安定させ、子供が自然に眠りやすくなる助けとなります。
ステップ3:寝る前の習慣を変える
授乳に代わる入眠儀式を作ることが、卒乳をスムーズに進める大きなポイントです。絵本の読み聞かせやオルゴール音楽など、毎晩決まった習慣を繰り返すことで、「これをしたら眠る時間」という条件反射が形成されます。また、寝る前の飲食を減らすことで、口腔内に糖分が停滞する時間を短縮でき、虫歯や歯茎の炎症リスクも軽減できます。
ステップ4:歯科医院での相談
「夜間授乳はいつまで続けても大丈夫か」「このままでは虫歯にならないか」といった不安を抱える患者様も多くいらっしゃいます。歯科医院では、子供の歯の生え方や噛み合わせ、口腔清掃の状況を確認したうえで、最適な卒乳時期や虫歯予防策について具体的に助言できます。また、必要に応じてフッ素塗布や定期的なチェックを行うことで、夜間授乳の影響を最小限に抑えることが可能です。
まとめ
夜間授乳は赤ちゃんの発育に大切ですが、「夜間授乳はいつまで?」という問いに対しては、1歳を目安に減らし、2歳までには卒乳を考えるのが望ましいといえます。長期の夜間授乳は虫歯や噛み合わせへの影響があるため、適切なタイミングで見直すことが重要です。やめられない場合も、歯や歯茎のケア、フッ素の利用、生活習慣の工夫で虫歯リスクを減らすことができます。患者様ごとに最適な方法を見つけるため、歯科医院での相談も取り入れていきましょう。
院長 椎名 康雅
最新記事 by 院長 椎名 康雅 (全て見る)
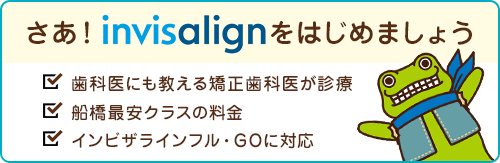
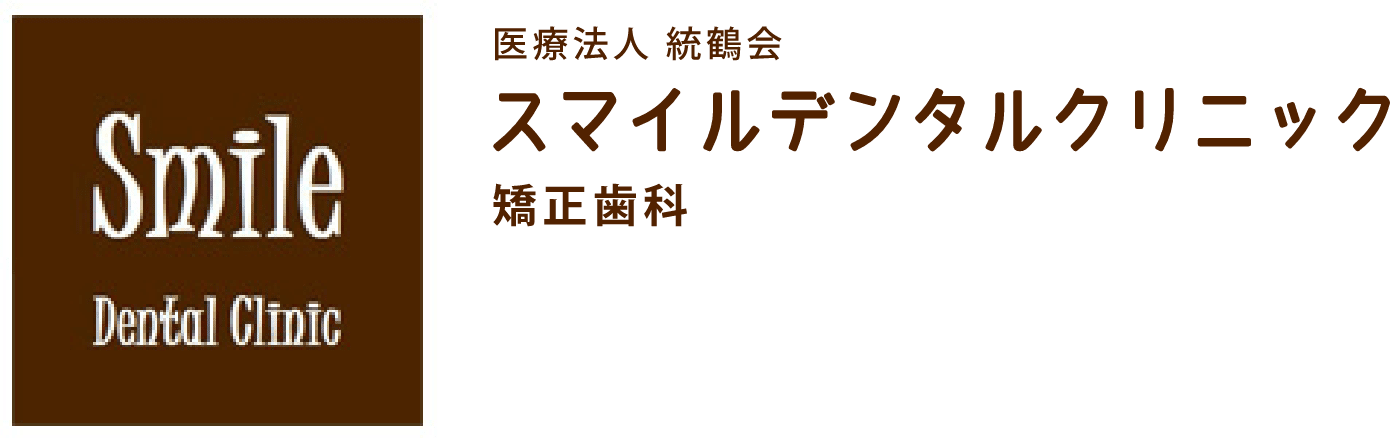
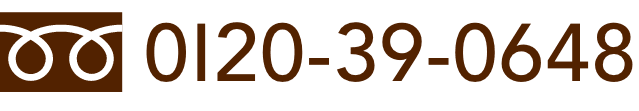
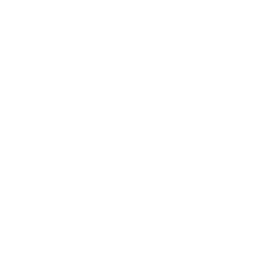 0120-39-0648
0120-39-0648